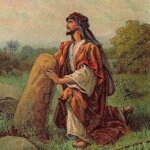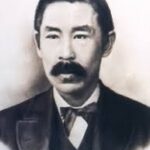久しぶりに
ある方に聖歌を使って励ましの手紙を送ろうと思いました。
それで久しぶりに、
YouTubeでアメージンググレイスを聞きました。
今までいろいろな方が歌うアメージンググレイスを聞きましたが、
今回のYouTubeのアメージンググレイスは、
英語で歌い英語の歌詞と日本語の訳詞が出ていました。
英語で聞きながら、今までに何度も聞き歌った 「歌詞」 をもう一度じっくり深く聴きました。
そして、
日本語の訳詞がこころに深く沁(し)みました。
あなたももう一度、じっくり深くこの賛美と日本語の訳詞を味わってください。
この記事の目次
「アメージング・グレイス」は、単に美しい歌ではなく、
ひとりの罪人が神のあわれみ(恵み)に捕まえられて救われた証の告白です。
まさに福音そのものです。ここでは次の流れでお話します。
-
聖歌229番「アメージング・グレイス」という賛美歌が生まれるまで
-
作者ジョン・ニュートンの人生(生い立ち〜どん底〜回心〜献身)
-
神様の導き(悔い改め、十字架、復活の福音とのつながり)
-
なぜ今も世界中で歌い継がれているのか
必要なところで聖書のメッセージも結びつけながらお伝えします。
1. 「アメージング・グレイス」はどんな歌?
「アメージング・グレイス(驚くばかりの恵み)」は、
イギリスの牧師ジョン・ニュートン(John Newton)が1772年ごろに書き、1779年に『オルニーの賛美歌集(Olney Hymns)』として出版された賛美歌です。
もともとの題名は「信仰のふり返りと期待で、
旧約聖書・歴代誌第一17章16-17節を土台にした説教のための歌、として書かれました。
歌詞は有名なこの言葉で始まります。
Amazing grace! (how sweet the sound) That saved a wretch like me! I once was lost, but now am found; Was blind, but now I see.
「なんという驚くべき恵みだろう。この恵みの響きはなんと甘いことか。
わたしのようなみじめな者を救ってくださった。 かつて私は迷っていたが、今は見いだされた。目が見えなかったが、今は見える。」
これはジョン・ニュートンが、自分の人生を神さまの前で正直に告白している”霊的自叙伝”です。
彼自身が「迷子」「盲目」「どうしようもない罪人」だった、と本気で認めているのです。
この歌は当初イギリスではそれほど有名ではありませんでしたが、のちにアメリカで大きく歌われるようになり、特に19世紀のリバイバル(第二次大覚醒)や黒人霊歌の文脈、そして公民権運動など「罪・苦しみ・差別・死」のただ中で神のあわれみを叫ぶ場面で何度も歌われ、世界中に広がっていきました。
でも、なぜそんなに心に響くのか? それは、書いた本人の人生が、まさに「地獄の底から十字架の前にひざまずいた人間」だからなんです。

2. ジョン・ニュートンという人の生い立ち
2-1. 子どものころ
ジョン・ニュートンは1725年、ロンドン近くのワッピングという港町に生まれました。父親は船乗りで商船の船長、母親は敬虔なクリスチャン家庭で「この子を牧師にしたい」と祈って育てていました。ところが母は、彼が6歳のときに病気(結核)で亡くなります。
母を失ってからのニュートンは、放り出されるように育ちます。11歳にはもう父の船に乗りこみ、荒っぽい海の世界に入ります。 少年の頃から反抗的で、乱暴で、口も悪く、神なんか信じないという態度の「どうしようもない若造」になっていきました。
彼自身、のちに「自分は神をあざけり、人を傷つけ、徹底的に道徳を捨てた」と書いています。これは単なる思春期の反抗ではなく、彼はのちに「自分は最悪の罪人、救われる価値もないほどの『wretch(みじめな者)』だった」と本気で言うほどの荒れぶりでした。
2-2. 奴隷貿易船の船員として
その後、彼はイギリス海軍に強制徴用されたり、逃げようとして罰を受けたり、とにかくトラブルだらけの人生を歩みます。やがて彼はアフリカ西岸とヨーロッパ・アメリカを結ぶ「奴隷貿易(アフリカ人を鎖で縛って運ぶ商売)」に深く関わるようになります。
正直に言えば、彼は人間を「荷物」のように扱う側にいました。命の重さを無視し、利益のために人を売り買いする、その最前線にいたのです。後年の彼はこの過去を「おぞましい罪」と表現し、涙ながらに悔い改め続けました。
3. 人生のどん底と「神よ、あわれんでください」
1748年。 ニュートンの乗った船がアイルランド沖で猛烈な嵐に襲われます。船は半壊。仲間は死にかけ。水がどんどん船内に流れ込み、沈没は時間の問題。自分も「今日で人生は終わりだ」と思ったその極限の中で、彼は思わずこう叫びました。
「神よ、あわれんでください!」
この叫びが、彼の人生の転換点になりました。
その瞬間まで彼はほぼ無神論的で、聖書も馬鹿にしていました。 でも死のふちで、彼は自分の罪・汚れ・高慢をはっきり見せられたんです。
ニュートンは後にこう振り返ります(要約):
-
自分は盲目だった。
-
神の前でどれほど罪深いかを、まったくわかっていなかった。
-
でも神はそんな自分を見捨てず、わたしの叫びを聞いてくださった。
これはアメージング・グレイス1節そのままです。
「迷っていたが、今は見いだされた。目が見えなかったが、今は見える。」
ここにすでに、悔い改めと信仰の核心があります。
-
悔い改めとは、単に「悪いことをしましたごめんなさい」ではありません。 神の前で「私は自分で自分を救えない」「私の心は汚れている」「私はあなたがいなければ滅びる」という『神に逆らい歯向かっていた罪びとであった』事実を認めることです。。
-
信仰とは、その自分のためにイエス・キリストが十字架で血を流されたことを信じて、神に立ち返ることです。
![]()
ニュートンはこの嵐の夜に「神は生きておられる。本当に私に憐れみをくださるお方だ」と心から叫び、神にしがみついたのです。
※ 重要な点 この夜が彼の”回心のはじまり”でしたが、すぐに全部がきれいになったわけではありません。彼はその後もしばらく奴隷船の仕事を続けています。完全にやめるのは1754〜1755年ごろ、つまり嵐から数年後です。 救いは一瞬で始まるけど、聖めは時間をかけて進んでいく──まさに「成長する悔い改め」の歩みでした。
これは、私たちにもとても大切な希望です。 「本気で悔い改めて信じたのに、まだ弱さが残ってる。じゃあ私はニセモノ?」 いいえ、そうではありません。ニュートンも同じ道を通りました。むしろその長い格闘が「恵みは驚くべきものだ」と彼に確信させていくことになるんです。
4. 牧師として、そして奴隷制度反対の証人として
ニュートンはついに海を降り、神学を学び、1764年にイングランド国教会の牧師として按手(任職)を受けます。最初の任地はイングランドのオルニーという小さな町でした。
オルニーの人々は貧しく、読み書きができない人も多かったのですが、ニュートンは高いところから説教する牧師ではなく、
「自分は本当にひどい罪人だった。
でもイエスキリストの十字架はそんな私をも救った」と涙ながらに自分のストーリーを語る牧師でした。
彼は「硬い心を砕き、傷ついた心をいやす」ことを自分の使命だと語っています。
この町で、同じくクリスチャン詩人ウィリアム・カウパー(William Cowper)と出会い、2人で多くの賛美歌を書きました。その集大成が『オルニーの賛美歌集』で、その中のひとつが「アメージング・グレイス」でした。
後年ニュートンは、かつて自分が関わった奴隷貿易の非人道性を公に告白し、奴隷制度廃止を求める側に立ちます。彼はイギリスの議会や若いリーダーたち(たとえばウィリアム・ウィルバーフォースに影響を与えたと言われます)に対し、奴隷交易がどれほど恐ろしく神に反する罪であるかを証言しました。
彼は「私はかつて盲目だった。だが今は見える」とだけでなく、「だからこそ、今は声を上げる」と生涯をもって示したのです。
つまり彼は、口先だけで「イエス様ありがとう」と言ったのではなく、悔い改めを行動で生きた人でした。
5. アメージング・グレイスの神学(福音とのつながり)
大切なポイント“福音”を信じたということ──
「自分自身の神様への罪をこころから悔い改め神様に立ち返り、自分自身の罪のためにイエス・キリストが十字架で身代わりに刑罰を受け死んでくださったこと、また死んで三日目によみがえられたこと」
まさにそれが「アメージング・グレイス」の心臓部です。
この賛美歌には、福音の三つの柱がはっきり出ています。
(1) わたしは本当に罪人だった(罪の告白)
「a wretch like me(こんなみじめな私)」と彼は歌います。
これは自己否定ではなく、神の聖さの前で本当の自分の姿を見た人の、正直な告白です。
ローマ書3章23節「すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けられない」。
ニュートンは「私は例外ではない」と言ったのです。
(2) しかしイエス・キリストの十字架はその私を救った(赦し)
イエスキリストは私たちの罪の身代わりとして十字架でさばきを受け、血を流し、死んでくださいました(イザヤ53章5-6、ローマ5章8)。
ニュートンは、ただ「神様は優しいから見逃してくれた」ではなく、「正しいさばきは十字架で支払われた。だから私は赦された」と理解しました。
彼はこの赦しを「grace(恵み)」と呼びました。恵みとは「もらう資格のない者に、ただでそそがれる神の好意」です。
(3) キリストは死を打ち破り、よみがえられた(新しいいのち)
イエスキリストは3日目によみがえり、死の力に完全な勝利を宣言されました。
(1コリント15章3-4)。
だから赦しは「気休め」ではありません。復活のイエスキリストは今も生きて働いておられ、盲目だった人間の心の目を開き、迷子だった魂を「見いだされた者」として神のもとに連れ帰るのです(ルカ15章の失われた羊・失われた息子のたとえとも深く響きあいます)。
ニュートンは「私は迷子だった(lost)けれど、いま見つけられた(found)」と歌います。
これは放蕩息子が父のもとに帰ったとき、父が言った「死んでいたこの子が生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ」(ルカ15章24節)と同じ響きです。
彼はまさに“放蕩息子”として神のところへ帰ったのです。

6. だからこの歌は今も力を持つ
「アメージング・グレイス」はいまや、教会だけでなく、葬儀、災害、戦争、差別、依存症からの回復集会、刑務所、病院…人が一番弱り、痛み、罪責感や喪失の重さに押しつぶされそうな場所で歌われ続けています。
なぜでしょう?
それは、
-
完璧な人の歌ではなく、
-
ボロボロだった罪人が神の前で泣きながら立ち上がった証言だからです。
ニュートンは自分の人生をこうまとめました、と伝えられています(有名な言葉):
「私は二つのことをよく知っている。 ひとつ、私はひどい罪人であること。 もうひとつ、キリストは偉大な救い主であること。」
この告白こそ「アメージング・グレイス」の心なのです。

まとめ
-
ジョン・ニュートンは1725年に生まれ、幼くして母を失い、荒れた青年期を送り、奴隷貿易に関わる「最悪の罪人」だったと自分で言っています。
-
1748年、激しい嵐の中で「神よ、あわれんでください」と叫んだことをきっかけに、彼は悔い改めと信仰の道に入ります。
-
やがて海の仕事と奴隷貿易から離れ、1764年に英国国教会の牧師になり、オルニーという町で人々に寄り添いながら福音を語りました。
-
1772年頃、彼は自分の救いの物語を「アメージング・グレイス」として歌詞にまとめ、1779年に『オルニーの賛美歌集』として出版しました。
-
その歌詞は、罪の告白・イエスキリストの十字架のあわれみ・復活による新しいいのち・そして「迷子だった私が、いまは見いだされた」という救いの喜びを、だれにでもわかる言葉で宣言しています。
-
後年ニュートンは、奴隷制度の恐ろしさを証言し、廃止のために声を上げました。悔い改めは彼の人生の実践となりました。
「アメージング・グレイス」は、”立派な人が神に近づいた歌”ではなく、”汚れた者がイエスキリストの十字架と復活のいのちに抱きしめられた歌”なんです。
だからこそ、今も私たちがそのままの自分で神の前に出る勇気をくれる賛美歌なのです。